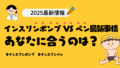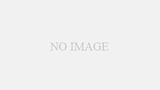糖尿病の方にとって、毎日の食事で「主食」をどうするかは大きな悩みではないでしょうか。ご飯やパンを食べると血糖値が急上昇してしまうのでは、と不安に思い、主食を抜いてしまおうと考えた経験がある方も多いかもしれません。確かに糖質を含む主食は食後血糖を上げますが、だからといって主食を完全に避けるのは得策ではありません。実際、毎食しっかり適量の主食をとり、主食だけに偏ったり抜いたりしないことが推奨されています。大切なのは主食の選び方と食べ方を工夫して、血糖値の急激な上昇を防ぐことです。この記事では、血糖値が上がりやすい主食はどれか、ご飯・パン・麺それぞれの特徴をやさしく解説し、GI値(※食品ごとの血糖値上昇の指標)も参考に血糖値への影響が大きい順にランキング形式で紹介します。主食を見直して、無理なく血糖コントロールに取り組むヒントにしてみましょう。
第1位:パン – 血糖値を最も上昇させやすい主食
主食の中で最も血糖値を上げやすいと言われるのがパン類です。精白された小麦で作る真っ白な食パンはGI値がおよそ90前後にもなり、これは高GI食品(GI値70以上)の代表格です。GI値(グリセミック・インデックス)とは食品ごとの血糖値上昇の度合いを示す指数で、ブドウ糖を100とした場合にどれくらい血糖が上がるかを示します。値が高いほど短時間で血糖値が急上昇しやすく、低いほどゆるやかに上がります。白い食パンは消化が早く食物繊維も少ないため血糖値が急上昇しやすく、糖尿病の食事では注意が必要です。実際、白米や精白パンなどはGI値が70以上と高く、食後の血糖を急激に上げるため注意すべき食品に挙げられています。特に菓子パン(甘いパン類)は糖質も脂質も多く、血糖コントロールに悪影響を及ぼすためさらに注意が必要です。クリームや餡の入ったパンやデニッシュは美味しい反面、砂糖やバターが多く血糖値だけでなくカロリーも過剰になりがちです。
とはいえ、「パン=悪者」と考えすぎる必要はありません。ポイントは種類と食べ方の工夫です。例えば全粒粉パンやライ麦パンなど、茶色いパンは精白パンに比べてGI値が低めです。全粒粉パンのGI値は50前後とされ、白い食パン(約91)のおよそ半分ほどの値です。これは食物繊維が豊富で消化吸収がゆるやかなためで、血糖値の上昇も穏やかになります。日本糖尿病学会も、玄米や全粒粉パンなどの未精製の穀物は白米や一般的なパンよりGI値が低いと報告しています。パンを主食にする場合は、できるだけ全粒粉やライ麦のパンを選ぶ、砂糖たっぷりの菓子パンは控えるなどの工夫をしましょう。また、パンは軽くて食べやすいため早食いや食べ過ぎにも注意が必要です。ゆっくりよく噛んで食べることで満腹感が得られ、血糖値の急上昇を抑えるのに役立ちます。例えば同じ食パンでも、バターやジャムをたっぷり塗って一度に2枚食べてしまうと血糖値も摂取エネルギーも過剰になります。適量を守りつつ、野菜やスープと一緒にゆっくり味わうことで、パンも上手に主食に取り入れることができます。
第2位:ご飯 – 日本人の主食、白米は高GIだが工夫で改善
日本の主食の代表であるご飯(白米)も、血糖値を上げやすい主食の一つです。白米のGI値は概ね84前後とされ、高GI食品の範疇に入ります。精白米はデンプンが消化されやすく、食後血糖が急激に上がりやすい特徴があります。白いご飯一膳を食べると「血糖が急上昇するのでは?」と心配になるかもしれませんが、実際その通りで白米は血糖値を急上昇させる食品です。特に糖尿病の方は食後高血糖を避けたいところなので、白いご飯の量や食べ方には気をつけましょう。しかし、ご飯もパンと同じく選び方・食べ方次第で血糖値への影響を和らげることができます。まず量に関しては、糖尿病食では1回の食事で摂取する炭水化物量(ご飯の量)を適切にコントロールすることが重要です。主治医や管理栄養士の指導に基づいた適量を守り、決して「お腹が空くのが怖いから…」といって白米を大盛りにしたり、おかわりを重ねたりしないようにしましょう。反対に、主食をまったく抜いてしまうのも望ましくありません。主食を抜くとかえってあとで空腹になり、ドカ食いや血糖コントロールの乱れにつながることがあるからです。
ご飯の種類を工夫することでも血糖値への影響は変わってきます。例えば、玄米や雑穀米に置き換えてみるのは非常に有効な方法です。玄米のGI値は56程度で、白米よりもかなり低く抑えられています。麦や雑穀を混ぜたご飯(五穀米など)もGI値が55前後と低めです。これら未精製の穀物には食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富に含まれ、消化吸収がゆっくりになるため血糖値の上昇が緩やかです。実際、「主食を白米から玄米に替えたところ、定期検査で血糖の数値が改善したと感じる」という糖尿病患者さんの声も報告されています。白いご飯しか受け付けないという方も、最初は白米に少しずつ玄米や押し麦を混ぜるなどしてみると抵抗なく始められるでしょう。また、最近ではもち麦や大麦をプラスしたご飯、あるいはカリフラワーライス(刻んだカリフラワーをご飯の代わりにする)など、糖質量とGI値を下げる工夫が色々登場しています。主食の内容を見直すだけでなく、食べる順番を工夫するのも効果的です。食事の際、いきなりご飯から食べ始めるのではなく、先に野菜のおかずや汁物、たんぱく質のおかずを食べ、その後にご飯をいただくようにすると血糖値の上昇がゆるやかになります。野菜や汁物でお腹が落ち着くことで白米の食べ過ぎも防げ、一石二鳥です。このように、ご飯は日本人にとって欠かせない主食ですが、「量」と「質」と「食べ方」の3点を意識するだけで血糖への影響をかなりコントロールすることができます。適量の範囲であれば怖がらずにご飯を取り入れ、どうしても心配な方は玄米や雑穀を活用してみましょう。
第3位:麺類 – 種類によってGI値が異なる主食、選び方で血糖コントロール
麺類は、ご飯やパンに比べると一概に血糖値への影響を語りにくい主食です。というのも、麺類には小麦で作られたうどんやパスタ、蕎麦粉を使ったそば、春雨(はるさめ)や中華麺、ビーフンなど種類が多く、それぞれGI値が異なるからです。例えば、精白小麦から作る柔らかいうどんはGI値が80程度と高く、白米と同じく血糖が上がりやすい食品です。一方で、同じ小麦製品でもパスタ(スパゲッティ)のGI値は65前後と中程度で、麺の中では比較的ゆるやかな部類に入ります。これはパスタの場合、デュラム小麦のセモリナ粉で作られており、しかもアルデンテ(ゆで過ぎず芯が残る状態)で調理すると消化が緩やかになるためです。そのため、日本糖尿病学会も「スパゲッティなどの麺類は白米や食パンよりGI値が低い」という研究結果に言及しています。さらに蕎麦粉が原料のそば(日本そば)のGI値は59程度と低めで、麺類の中では血糖値を上げにくい代表と言えるでしょう。特に十割そば(蕎麦粉100%)であれば食物繊維も多く、糖尿病の方にはおすすめの主食です。同じ麺類でも選ぶ種類によって血糖値への影響を抑えられることが分かります。もし麺類が好きな方は、うどんより蕎麦を選ぶ、パスタもクリーム系より野菜やオリーブオイルを使った和風・ペペロンチーノ系にする(砂糖の多いケチャップソースを避ける)など、小さな工夫で血糖値対策につなげられるでしょう。
麺類を主食にする際には、調理法や一緒に食べるものにも目を向けてみましょう。麺そのもののGI値が低くても、調味料やトッピング次第で血糖への影響は変わります。例えば、ラーメンは麺そのものの炭水化物に加えてスープにたっぷり油脂が含まれ塩分も多く、血糖管理の面で注意が必要なメニューです。油が多い食事は一時的に血糖値の上昇を緩やかにすることがありますが、長期的にはインスリン抵抗性を悪化させる可能性が指摘されています。つまり脂っこいラーメンは血糖値だけでなく将来的な代謝にも負担をかけかねません。また、麺類はつるつると食べやすいため早食いや大盛りにも注意です。腹八分目を心がけ、野菜たっぷりのスープやおかずと一緒にゆっくり食べるようにすると良いでしょう。近年では糖質制限中でも楽しめる低糖質麺も市販されています。糖質0g麺(こんにゃくを主原料にした麺)などはほとんど血糖値を上げないので、どうしても麺を思いきり食べたいときに利用するのも一つの手です。さらに市販の乾麺では、大豆麺や全粒粉入り麺など低GI・高たんぱくの製品も登場しています。これらを上手に活用し、麺類も工夫しながら取り入れれば、主食のバリエーションが広がりストレスも減るでしょう。
まとめ:主食の賢い選び方で血糖値を安定させましょう
ご飯・パン・麺、それぞれの主食が血糖値に与える影響についてランキング形式で見てきました。一般的には、パン(特に白い食パンや菓子パン)が最も血糖を上げやすく、次いで白米、麺類は種類を選べば比較的血糖値が上がりにくいと言えます。しかし、だからといって「血糖値のために主食は一切ダメ」ということでは決してありません。糖尿病の食事療法で大切なのは、「〇〇は禁止」と我慢することではなく、血糖値が安定しやすい食習慣を身につけることだと専門家も強調しています。今回挙げたように主食の種類を工夫するだけでなく、食べる順番を野菜・たんぱく質→主食の順にする、よく噛んでゆっくり食べる、適切なエネルギー量に抑えるといった基本も忘れずにいたいですね。幸いなことに、玄米ご飯や全粒粉パン、蕎麦や低糖質麺など、美味しく食べられて血糖値が上がりにくい主食の選択肢はたくさんあります。完全に主食を我慢する必要はありません。まずはできる範囲で主食を見直し、明日からの食事に無理なく取り入れてみましょう。主食を賢く選び上手に付き合うことが、きっと血糖コントロールの力強い味方になってくれるはずです。
参考文献・情報ソース: 日本糖尿病学会『健康食スタートブック』、厚生労働省『日本人の食事摂取基準』、お茶の水橋交番横クリニック、グッドライフクリニック、リバーシティクリニック東京、他.