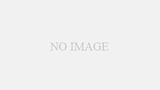今年も蒸し暑い夏がやってきました。中高年の2型糖尿病をお持ちの方にとって、真夏の高温環境はとくに心配ですよね。汗をかきすぎて脱水になったり、熱中症になってしまわないか、血糖コントロールは大丈夫だろうかと不安に感じることもあるでしょう。しかし、大丈夫です。正しい知識と対策があれば、暑い季節でも安心して過ごすことができます。この記事では、夏場の脱水・熱中症予防と血糖管理のポイントについて、女性記者の視点からやさしく解説します。暑さが糖尿病に与えるリスクや発汗と血糖値の関係、水分補給のコツ、外出時や冷房使用時の注意点、さらに血糖自己測定や食事・運動習慣の調整方法まで、盛りだくさんの内容です。適切な知識を身につけ、しっかり準備を整えて、一緒に夏を元気に乗り切りましょうね。
夏の高温環境が糖尿病患者に及ぼすリスク
真夏の高温多湿な環境は、糖尿病をお持ちの方にとって脱水症状や熱中症のリスクを高めます。その理由の一つは、糖尿病による神経障害などで汗をかきにくくなることです。本来、私たちの体は暑いときに汗をかいて熱を発散し、体温を調節しています。しかし糖尿病があると発汗機能が低下しやすく、体温調節がうまくいかなくなる傾向があります。また血糖値が高い状態が続くと腎臓から糖と一緒に水分が大量に排出されるため、体内の水分不足(脱水)を起こしやすくなります。こうした要因が重なり、糖尿病のある人はない人に比べて熱中症になるリスクが高いと言われています。
さらに高齢の糖尿病患者さんでは、喉の渇きを感じにくい傾向があり、気づかないうちに水分不足が進行しがちです。暑い屋外でなくても、気温の高い室内で過ごしている間に脱水症状になってしまうケースもあります。脱水が進むと血液中の水分が減って血糖値が急上昇することがあります。汗で失われた水分を補えず血液が濃くなるためです。その結果、体調が悪化して高浸透圧高血糖症候群(HHS)という重篤な状態に陥り、意識障害を起こす危険もあります。逆に、猛暑で食欲が低下して食事量が減ったり、暑さに体力を奪われたりすると低血糖になるリスクもあります。特にインスリン治療中の方やSU剤(血糖降下薬)を使っている方は、夏場の体調変化に合わせたきめ細かな調整が必要です。
このように、夏の暑さは糖尿病患者さんの血糖コントロールに様々な影響を与えますが、適切に対策すれば必要以上に恐れることはありません。まずは、「なぜ糖尿病の人は熱中症になりやすいのか」「暑さで血糖がどう変動しうるのか」を理解し、次項から具体的な予防策を見ていきましょう。知識を持つことで不安を減らし、安心して夏を過ごす土台を作ることができます。
発汗と血糖コントロールの関係
汗をかくことは私たちの体温を調節する大切な機能です。汗が蒸発するときに熱を奪い、体を冷やしてくれます。しかし糖尿病がある方は、前述のように発汗機能が低下しやすい傾向があります。長期間血糖コントロールが不良だと自律神経に障害が及び、暑くても汗をかきにくくなったり、必要な量の汗が出なかったりすることがあります。その結果、体に熱がこもりやすくなり、体温が上昇してしまいます。体温調節がうまくいかないと熱中症に直結するため、糖尿病の方ほど注意が必要なのです。
一方で、暑い環境で大量に汗をかくと体内の水分と一緒に電解質(塩分など)も失われます。水分補給が追いつかず脱水状態になると、血液中の水分が減って血糖値が上昇しやすくなります。実際、発汗で体重のわずか2%の水分が失われただけでもパフォーマンスに悪影響が出るという報告があります。水分不足で血液がドロドロになると血流も悪くなり、インスリンや血糖を調節するホルモンの働きにも影響が出る可能性があります。つまり、汗をかかないこともかきすぎて水分を失うことも、どちらも血糖コントロールに悪影響を及ぼしうるのです。
ではどうすれば良いのでしょうか?ポイントは二つです。まず、日頃から適切に血糖管理を行うこと。血糖値が安定していれば自律神経機能も保たれ、汗による体温調節機能が正常に働きやすくなります。もう一つは、汗をかいた分の水分補給をこまめに行うことです。【「汗が出にくい」「暑いのにあまり汗をかかない」】と感じる方は、実は体内の水分不足が原因かもしれません。軽い脱水になると汗の分泌量自体が減ってしまい、体温がさらに上がってしまう悪循環があります。喉の渇きに頼らず、早め早めの水分摂取で汗が適切に出る状態を維持することが、血糖コントロールにも熱中症予防にも大切です。
また、汗をかくと血糖値が下がるイメージを持つ方もいるかもしれません。確かに暑さの中で体力を消耗すればエネルギーが使われ一時的に血糖が下がることもありますが、脱水による血糖上昇リスクのほうが大きい点に注意しましょう。暑い日の体調変化で血糖値が乱高下しないよう、次に述べる水分・塩分補給のコツを実践してみてください。
水分と塩分補給のポイント
こまめな水分補給は、夏を乗り切る上で何より大切です。人間の体は、喉が渇いたと感じたときにはすでに軽い脱水状態になっているとも言われます。特に糖尿病の方や高齢の方は渇きを感じにくいことがありますので、「喉が渇く前に少量ずつ飲む」ことを意識しましょう。具体的には、起床時、外出前、食事中や食後、入浴前後、就寝前など、日常の節目節目にコップ半分~1杯程度の水分を摂る習慣がおすすめです。一度に大量に飲む必要はありません。むしろ一気にがぶ飲みすると体内の電解質バランスが崩れる恐れがあるため、少量をこまめにが基本です。日常的な水分補給には、水や麦茶、薄めのお茶など糖分の入っていない飲み物が最適です。
では、塩分補給は必要なのでしょうか?CMなどで「汗をかいたら塩分も取ろう」とよく言われますが、ふだん3食きちんと食べている方であれば、基本的に食事から十分な塩分を摂取できています。日本人は平均して1日約10gもの食塩を摂っているとされ、これは厚生労働省の目標量を大きく上回る量です。したがって、日常生活や軽い運動で少し汗をかく程度なら水やお茶で十分で、わざわざスポーツドリンクや塩タブレットで塩分を追加する必要はほとんどありません。特に高血圧をお持ちの方は、夏でも1日6g未満の減塩が推奨されますので、塩分の摂り過ぎにならないよう注意しましょう。
とはいえ、真夏の炎天下で長時間作業したり屋外スポーツをする場合、大量の汗とともにナトリウム(塩分)が失われます。そのような大量発汗時には水分と一緒に適度な塩分補給も必要です。汗でナトリウムが欠乏すると、喉が渇く感覚が麻痺してしまい、必要な水分補給ができなくなることがあります。このため、酷暑下では塩分濃度0.1~0.2%程度の経口補水液(ナトリウム40~80mg/100mL)を飲むのが有効です。市販の経口補水液(例:OS-1など)はナトリウムやカリウム等の電解質を適切に含み、糖分はスポーツドリンクより少なめに調整された医療用飲料です。脱水症状の予防・改善に効果的ですが、脱水状態でない日常の水分補給として常用するものではありません。経口補水液には塩分が多く含まれるため、普段から塩分制限のある方が漫然と飲むと塩分過多になる恐れがありますし、糖質も含むため血糖値にも影響します。必要かどうか判断が難しい場合は、自己判断で大量に飲まず医師や管理栄養士に相談してから取り入れると安心です。
同様に、一般的なスポーツドリンクにも注意が必要です。確かにスポーツドリンクは汗で失われた電解質を含み、吸収も早いよう組成されていますが、一方でエネルギー補給のため多量の糖分が含まれています。市販のものでは500mLペットボトルに角砂糖8個分(約24g)の糖が入っている例もあります。糖尿病の方がこうした飲料をがぶがぶ飲めば血糖値が急上昇するリスクが高まります。また糖分の多い飲み物は飲んでも喉の渇きが十分に癒えず、つい飲みすぎてしまう悪循環に陥りがちです。したがって、「水や麦茶+場合に応じて少量の塩分補給」くらいが基本のスタンスと考えましょう。どうしても塩分補給が気になる方は、ノンシュガーの電解質ドリンクや塩分タブレットを利用する手もあります。塩タブレットなら1錠でスポーツドリンク100mL相当の塩分(0.1g)をわずか11kcalで補えるものもあり、糖分を摂らずに塩分だけ補給するのに便利です。ただし塩タブレットも舐めすぎには注意し、目安として1日2~4個程度にとどめましょう。
最後にもう一つ、水分補給で避けたい飲み物について触れておきます。アルコール飲料やカフェインを多く含む飲料(コーヒーや紅茶、緑茶など)は利尿作用があるため、せっかく飲んだ水分が尿として排出されやすく、かえって脱水を進めてしまう恐れがあります。例えばビールは一時的に喉の渇きが癒えても実は体内の水分を奪ってしまうので、「汗をかいた後の一杯」が習慣になっている方は注意しましょう。どうしてもという場合はアルコールは控えめにし、その分水を余計に飲むくらいの意識でいてくださいね。
夏の外出時に気をつけたいこと(服装・持ち物・移動時間帯)
暑い夏に屋外へ出かける際には、熱中症対策を万全に行いましょう。まず服装ですが、ポイントは体に熱をこもらせないことです。通気性が良く、汗を吸いやすく乾きやすい素材(吸湿速乾素材など)の衣服を選び、体を締め付けないゆったりとした服装を心がけてください。色は白やパステル調などの明るい色がベターです。黒っぽい服は日光を吸収して生地の温度が上がりやすいため、避けた方が無難です。外出時には帽子や日傘も積極的に活用しましょう。直射日光を頭や体に浴び続けると体温がぐんぐん上昇してしまいます。帽子は通気性のあるつば広のものが理想的です。日傘も最近は男性用含め色々出ていますので、恥ずかしがらずに使ってくださいね。炎天下では日陰を上手に利用し、こまめに休憩を取ることも大切です。
外出の時間帯にも工夫しましょう。最も気温が上がる11時~15時頃の外出は可能な限り控え、用事は朝のうちか日が沈んでからにシフトするのがおすすめです。【「どうしても日中に出かけざるを得ない…」】という場合は、こまめに屋内に入って涼む、一気に歩かず日陰で休み休み進む、水分を普段以上に補給する等、無理のない計画を立ててください。天気予報で猛暑日や高湿度が予想される日は、無理に外出予定を入れず**「暑さ指数」**などの情報も参考にしながら行動を判断しましょう。最近はスマホアプリやニュースでその日の熱中症リスクが確認できますので、ぜひ活用してください。
持ち物の準備も万全にします。まず飲み物は必ず携帯しましょう。途中で買えるだろうと油断せず、最初から水やお茶のボトルを持って出る習慣をつけてください。長時間の外出や運動をする場合は、先述の塩タブレットや必要に応じ少量のスポーツドリンク(できれば低糖タイプ)も持参すると安心です。次に、携帯扇風機や冷感グッズも有用です。電池式のミニ扇風機や、首に巻くクールタオル・冷却ジェルシートなどは体感温度を下げてくれます。保冷剤をハンカチに包んで首元や脇の下を冷やすのも効果的ですよ。
糖尿病患者さんならではの必携品としては、低血糖対策の補食があります。暑さの中では予定外にエネルギーを消耗したり、食事時間がずれ込んだりして低血糖を起こす危険もあります。万一に備え、ブドウ糖タブレットや砂糖入りの飴、ジュースなど即座に血糖を上げられるものを必ず携行してください。あわせて糖尿病であることを示すIDカードや緊急連絡先のメモなども持っていると、いざというとき周囲の助けを得やすくなります。スマートフォンの医療ID機能にあらかじめ自分の病気や服薬情報を登録しておくのも良いでしょう。
もしインスリン注射を使用している方は、インスリン製剤の温度管理にも気を配りましょう。インスリンは高温にさらされると劣化し、効果が低下してしまいます。夏場に外出する際はインスリンペンや予備のインスリンを冷房の効いた室内に置きっぱなしにしないよう注意が必要です。日差しの強い屋外に持ち歩く場合は、保冷ポーチや保冷剤とともに携行し、直射日光や車内の高温から守ってください。また、外出時には**血糖測定器具(血糖計やセンサー、穿刺具、試験紙)**も忘れずに持参しましょう。予定の変更や食事の遅れなどで血糖コントロールが必要になったとき、すぐ血糖値を確認できると安心です。これらの準備を整えておけば、出先で体調に不安を感じても慌てず対処できますね。
最後に、できれば一人での外出は避けるか、周囲に行き先や帰宅時間を伝えておくとより安全です。特に猛暑日の外出は家族や友人に付き添ってもらうか、「〇時に帰宅します」と誰かに伝言しておくと良いでしょう。万一体調が悪くなっても連絡・救助を得やすくなります。帽子や日傘、水分など十分な備えをしていても、急にくらっときたり吐き気が出たりすることもありえます。そんなときは無理せず周囲に助けを求め、速やかに休むか医療機関を受診してください。安全第一で行動し、暑い日のお出かけを乗り切りましょう。
冷房(エアコン)使用時の注意点
暑さ対策には冷房(エアコン)の活用も欠かせません。熱中症は高温多湿の環境で起こる全身障害ですが、エアコンで室温と湿度を適切に下げれば予防できるとされています。実際、猛暑日の室内でエアコンをつけずに我慢していると、室内にいても熱中症に陥る危険があります。東京都内で熱中症により亡くなった方の調査では、屋内で亡くなったケースの約45%はエアコンがOFFになっていたそうです。また約30%はそもそもエアコンが設置されておらず、10%は故障して動かない状態でした。つまり、「エアコンを適切に使っていれば防げた可能性が高い」ことをこの数字は示唆しています。高齢の方の中には電気代や体への負担を気にして冷房を極力使わない方もいますが、エアコンは命綱と思って上手に使いましょう。
まず設定温度ですが、外気温にもよりますが25~28℃前後が目安とされています。部屋の広さや個人差もありますので、「寒すぎず暑すぎず快適」と感じる範囲で構いません。冷えすぎるのが心配な場合は、冷房ではなく除湿モード(ドライ)を使うのも効果的です。湿度が下がるだけでも体感温度はかなり違います。反対に、エアコンの効いた部屋で薄着のまま長時間過ごして体を冷やしすぎることにも注意です。汗腺が閉じて汗をかきにくい体になってしまい、急に暑い屋外に出たときに体温調節ができなくなる恐れがあります。冷房の利いた室内では薄手の上着やスカーフで体を冷やしすぎないよう調整しつつ、適度に外気に当たる時間を作るのも良いでしょう。例えば、オフィスで一日中冷房に当たった日は、帰宅後にぬるめのお風呂にゆっくり浸かって体を温め直すなど、自律神経のリセットを意識してみてください。
エアコン使用中も水分補給を忘れずに。涼しい室内にいると汗をかかないぶん喉の渇きを感じにくくなり、気付かないうちに脱水が進むことがあります。特に夜間寝ている間は誰でも脱水ぎみになりますので、寝る前にコップ1杯の水を飲む、夜中に目が覚めたときも一口含む、といった習慣を持つと良いでしょう。【「エアコンの風が苦手…」】という方は扇風機やサーキュレーターを併用し、直接冷風が当たらないよう風向きを工夫してください。冷房と併用して部屋の空気を循環させることで、冷えすぎを防ぎつつ室温を均一に保てます。フィルターの掃除やリモコンの電池チェックなども忘れずに行い、エアコンが正常に動作する状態をキープしましょう。独り暮らしの高齢者の方は、周囲のご家族もぜひ「ちゃんとエアコン使っているかな?」と気にかけてあげてください。
また、屋内外の温度差にも注意です。冷房の効いた室内から炎天下に急に出ると、体がびっくりしてしまいます。可能であれば家を出る5~10分前にはエアコンを切り、少し室温を上げておくか、外に出た直後は日陰でしばらく慣らすなどして温度差を緩和しましょう。車移動の場合も同様で、冷房の効いた車から外に出るときはゆっくり歩き、すぐに直射日光を避けるようにします。反対に、炎天下から冷房の強い部屋に飛び込んだときにも体調不良が起こることがあります。大量に汗をかいた状態で急激に体を冷やすと、自律神経が乱れてめまいや腹痛を起こす人もいます。汗で冷えた衣服は着替え、冷房の部屋ではまず扇風機の風で汗を蒸発させてから強い冷風に当たる、といった工夫で体への負担を減らしましょう。
夏場における血糖自己測定のポイント
夏は普段以上に血糖変動に気を配る必要があります。高温環境では脱水や食生活の変化により血糖値が上がりやすくなる一方、食欲不振や運動量の低下で下がることもあり、いつも以上に不安定になりがちです。そのため、自己血糖測定(SMBG)を行っている方は測定回数を増やすことを検討してください。【「いつも朝晩しか測らない」という方も、】暑い時期だけでもこまめに測定しておくと安心です。特に猛暑日の午後や外出後、運動後など、血糖値が普段と違う動きをしそうなタイミングでは、一度チェックしてみると良いでしょう。【「暑さでフラフラするけど、これは低血糖?それとも単なる熱疲労?」】と判断に迷う場合にも、血糖を測ってみれば原因の切り分けができます。暑さによる体調不良と低血糖は症状が似ていることがあります。どちらも冷や汗やめまい、動悸などを起こすため戸惑いますが、血糖測定で数値を確認すれば適切な対処につながります。
インスリン注射や血糖降下薬(SU剤など)を使用中の方は、夏場は低血糖にも注意が必要です。汗をかくほどの活動をした後や、食事量が減ったときなどは予想以上に血糖が下がるケースがあります。普段以上に体調の声を聞き、「少し手が震える」「動悸がする」などいつもと違う感覚があれば、すぐ血糖を測ってみましょう。必要なら前述の補食(ブドウ糖など)で早めに対処し、重症化させないことが大切です。また、逆に高血糖になりすぎていないかもチェックが必要です。脱水が進むと血糖値が急上昇し、酷い場合はケトアシドーシスという危険な状態に陥る可能性があります。喉の渇きや倦怠感、尿量減少など「もしや脱水?」と思うサインがあれば、その時点で血糖値も測定してください。いつもより明らかに高い値であれば、早急に水分・電解質を補給し、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
測定データは夏の体調管理の指標として大いに役立ちます。例えば、「猛暑日が続くと朝の血糖が普段より高めに出るな」とか「寝苦しい夜があった翌日は乱高下しやすい」など、自分の体の傾向が見えてくるかもしれません。その場合は主治医に相談し、夏場だけインスリンや薬の量を微調整するといった対応も検討されます。定期受診も暑いからといって先延ばしにせず、夏の間もきちんと受診してください。血糖値の記録や体調のメモを持参すれば、医師も季節に応じたアドバイスをしやすくなります。最近では連続血糖測定器(CGM)を使用している方もいるでしょう。センサー貼付部分に汗をかくとかゆみが出たり剥がれやすくなったりすることもありますので、テープの補強や汗対策もお忘れなく。夏はつい面倒で自己測定を怠りがちですが、「見えない血糖変動を見える化する」ことで猛暑によるリスクを最小限に抑えましょう。
食事や運動習慣の調整ポイント
食生活と運動習慣も、夏に合わせた工夫が必要です。暑いとどうしても食欲が落ち、「そうめんだけで済ませてしまう」「つい冷たいアイスや甘いスイカを食べ過ぎてしまう」といったことはないでしょうか。猛暑による食事内容や運動量の変化は血糖コントロールを乱す一因となります。まず食事ですが、食欲が無いからと炭水化物(麺類・かき氷など)ばかりをツルッと食べてしまうと、後で血糖値が急上昇しやすくなります。また冷たい飲み物やデザートの過剰摂取で胃腸が冷えると消化不良を起こし、せっかく摂った栄養が吸収されにくくなることもあります。栄養バランスを意識しつつ、調理法を工夫してみましょう。例えば、暑い日は火を使った煮込み料理は敬遠しがちですが、そんな時は電子レンジや湯通しを活用して簡単な冷製おかずを作ってみてください。オクラやモロヘイヤなど夏野菜を刻んで冷奴にかければ、さっぱりしながらビタミンや食物繊維、たんぱく質も摂れます。鶏むね肉をゆでて裂き、きゅうりと和えて中華風の冷菜にするのもおすすめです。酢の物や梅干しなど酸味のある食品は食欲を増進させますし、適度な塩分補給にも役立ちます。糖尿病の方向けの夏レシピはインターネットや病院の栄養指導でも数多く紹介されていますので、「夏 糖尿病 レシピ」などで検索してみるのも良いでしょう。
また、食中毒予防にも気を配りましょう。夏場は高温多湿で食品が腐りやすく、食あたりを起こすと激しい下痢や嘔吐で一気に脱水状態に陥ってしまいます。下痢や嘔吐は血糖コントロールにも大きな乱れを生じさせます。冷蔵庫を過信せず、生鮮食品は早めに使い切る、一度出した食べ物は長時間室温に放置しない、水分の多い料理は小分けにして冷やす等の対策を徹底してください。万一食中毒や夏風邪で発熱・下痢・嘔吐などの症状が出た場合は、早めに医療機関を受診するとともにシックデイ対応(こまめな血糖測定、水分と糖分の補給、必要ならインスリン量調整など)を行いましょう。症状が軽くても「まあいいか」と放置せず、体調が悪いときこそ血糖値の動きに注意が必要です。
運動については、夏場は時間帯と場所の選び方がポイントです。運動療法は血糖コントロールに有効ですが、炎天下で無理に続けると熱中症のリスクが高くなって危険です。日中の暑い時間帯(特に11~15時)を避け、朝早くか夕方以降の涼しい時間に切り替えましょう。例えば朝の散歩を日課にする、夕食後に近所をゆっくり歩いてみるなど、できる範囲で構いません。どうしても日中に運動したい場合は、冷房の効いた室内で行う工夫をしましょう。スポーツジムやショッピングモール内のウォーキングコース、地下通路など涼しい環境を利用すると安心です。ご自宅でも、エアコンをつけた部屋でYouTubeのヨガ動画を見ながら軽く体を動かす、といった形であれば安全に運動不足を解消できます。
運動時には、いつも以上に無理をしないことが大事です。「汗をかくほど頑張ったほうが健康に良い」と思うかもしれませんが、夏は短時間でも毎日続けることに意味があります。体調が優れない日は思い切って休息をとり、体力の回復に努めてください。逆に冷房の効いた環境でずっと体を動かさないでいると、汗をかく機能が衰えてしまいます。少し汗ばむくらいの運動や入浴で適度に汗をかく習慣も維持しましょう。つまり、「休む」と「動く」のメリハリをつけることが夏の運動のコツです。なお、高温環境下での運動は心拍数が普段より上がりやすくなります。心臓に負担を感じたらすぐペースを落とし、木陰で休憩するなど安全第一で行動しましょう。
薬を服用している場合は、薬剤と脱水の関係にも留意が必要です。たとえばSGLT2阻害薬(グリフロ剤)という糖尿病治療薬を使っている方は、尿から糖と一緒に水分も排出する作用があるため、夏場は特に脱水に陥りやすくなります。服用中の方は普段以上にこまめな水分補給を心がけましょう。また糖尿病以外でも、利尿薬(むくみや高血圧の薬)や抗ヒスタミン薬(アレルギーの薬)には体を乾燥させやすいものがあります。ご自身の薬について不安があれば、次回診察時に「夏場に注意すべきことはありますか?」と医師や薬剤師に相談してみてください。
最後になりますが、自分の体の変化に敏感になることも大切です。毎日の朝の体重測定は脱水予防に役立ちます。昨日より急に0.5~1kg以上体重が減っていたら、汗や尿で水分が失われた可能性があります。また尿の色もチェックしましょう。濃い黄色で量が少なければ脱水気味のサインです。口の中の渇きや倦怠感、めまいなども要注意の兆候です。こうした変化にいち早く気付くために、毎朝の体調チェックを習慣にしてください。そして、少しでも「おかしいな」と思ったら無理をせず休む勇気を持ちましょう。「まだ大丈夫」と我慢してしまうのが一番いけません。体は正直ですから、サインを見逃さないことが何よりの予防策です。
猛暑の時期は、糖尿病をお持ちの方にとって血糖管理だけでなく脱水や熱中症といったリスクにも注意が必要です。しかし今日お伝えしたように、十分な知識と対策があれば過度に心配する必要はありません。ポイントは「暑さを避ける工夫」「水分・電解質を切らさないこと」「自分の体調の変化をこまめに確認すること」の三つです。日々のセルフケアと主治医など医療者との連携によって、夏のリスクを最小限に抑えることができます。どうか無理をせず、ご自身の体と対話するような気持ちでこの夏を乗り切ってくださいね。【「ちょっとしんどいな」】と感じたら早め早めの休息・水分補給・受診を心がけ、健康第一でお過ごしください。私たちも陰ながら応援しています。一緒に安心で楽しい夏を過ごしましょう!