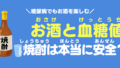糖尿病と歯周病――一見すると無関係に思えるこの2つの病気が、実は深く関わり合っていることをご存知でしょうか。糖尿病患者さんは日々血糖コントロールや合併症に気を配っていますが、「歯ぐきの健康」については見落とされがちです。しかし近年、糖尿病と歯周病は互いに影響を及ぼし合う“双方向の関係”にあることが明らかになり、歯周病は「糖尿病の第6の合併症」とまで呼ばれています。本記事では女性記者の視点から、この知られざる双方向リスクについて最新の知見を交えながらやさしく解説し、糖尿病と歯周病の双方から健康を守る実践的なアドバイスをお届けします。
まずは糖尿病と歯周病、それぞれがどのような病気なのか簡単におさらいしてみましょう。糖尿病は血液中の血糖値が慢性的に高くなる病気で、1型糖尿病(自己免疫等でインスリンがほとんど分泌されないタイプ)と、2型糖尿病(生活習慣などが原因でインスリンの作用不足が起こるタイプ)に大別されます。日本では糖尿病が強く疑われる人と予備群を合わせて約2,000万人に上ると推計されており、まさに国民病ともいえる存在です。糖尿病は進行すると網膜症・腎症・神経障害といった深刻な合併症を引き起こすため「万病のもと」と称されます。
一方の歯周病は、歯と歯ぐきの境目にプラーク(歯垢)がたまり、歯ぐきが炎症を起こすことで進行する病気です。放置すれば歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちる原因にもなり、むし歯と並んで日本人が歯を失う主要因となっています。実際、歯周病は非常に身近な疾患で、日本では歯周病で治療を受けている患者数が約1,135万人にも上るとの調査結果があります。こうした歯周病は以前から全身の健康への影響が指摘されていましたが、なかでも糖尿病との関係が注目されるようになりました。

糖尿病が歯周病に与える影響:高血糖が招く歯ぐきへのダメージ
糖尿病の方は健常な方に比べて歯周病になるリスクが格段に高いことがわかっています。ある研究では糖尿病患者は重度の歯周病を発症するリスクが約3倍に達するとの報告があり、特に血糖コントロールが不十分な場合にその傾向が顕著です。血糖値が慢性的に高い状態(高血糖)が続くと、私たちの体の免疫機能に乱れが生じます。具体的には、細菌に対抗する白血球の働きが弱まり、歯周病の原因である歯周病菌に対する抵抗力も落ちてしまうのです。その結果、糖尿病の人は歯ぐきの感染症にかかりやすく、歯周病が悪化しやすくなります。
さらに、高血糖状態は体の炎症反応にも影響を及ぼします。糖尿病では炎症を調節する仕組みが乱れ、歯ぐきで起きた炎症が過剰に反応しやすくなります。歯周組織に炎症が起きると、サイトカインと呼ばれる物質が放出されますが、糖尿病の高血糖環境ではこのサイトカインの働きが過剰になりがちです。サイトカインは本来、免疫細胞が感染と戦うために出す「炎症のメッセンジャー」ですが、これが過剰になると歯を支える骨を溶かす「骨吸収」を促進し、歯周病を一層悪化させてしまいます。つまり糖尿病があると歯周病菌への抵抗力低下と炎症の暴走という二重のダメージで、歯周病が進行しやすくなるのです。その上、糖尿病患者さんでは歯周病の治療効果も出にくく、治りづらいことが知られています。こうした理由から、糖尿病の人にとって歯周病は非常に注意すべき合併症だといえます。

歯周病が糖尿病に与える影響:見逃せない“第6の合併症”
では逆に、歯周病にかかっていることが糖尿病にどのような影響を与えるのでしょうか。実は歯周病により糖尿病の管理が難しくなることも分かってきています。重度の歯周病になると歯ぐきは慢性的な炎症状態にあり、炎症部位から放出された物質(前述のサイトカインなど)が血管を通じて全身に巡ります。その結果、体のインスリン(血糖を下げるホルモン)に対する反応性が低下し、インスリン抵抗性が悪化してしまうのです。いわば歯ぐきの炎症が全身に波及し、血糖値を下げる力を弱めてしまう状態といえます。このため歯周病のある人は血糖コントロールが乱れやすく、糖尿病が悪化しやすくなるという悪循環に陥りがちです。臨床的にも、歯周病が進行した糖尿病患者ではヘモグロビンA1c(HbA1c)の値が高くなりがちとの報告があります。さらに最近の研究では、重度の歯周病を抱える人は将来的に糖尿病を発症するリスク自体も高まる可能性が示唆されています。このように歯周病は糖尿病を悪化させるだけでなく、新たな糖尿病発症リスクにまで関与する可能性があるため、糖尿病患者さんにとって見逃せない存在です。
歯周病が「糖尿病の第6の合併症」と呼ばれるゆえんも、ここにあります。糖尿病の三大合併症(網膜症・腎症・神経障害)や大血管障害(心筋梗塞・脳梗塞など)と比べると歯周病は命に直結しないように思われるかもしれません。しかし歯周病があると心臓病や全身の死亡リスクが上がることまで報告されており、全身の健康に大きく関わる問題なのです。また興味深いことに、日本の大規模調査では、糖尿病患者が定期的に歯周病治療を受けていると腎症の進行が抑えられ、将来的な人工透析への移行リスクが32~44%も低下したとの結果も示されました。これは歯周病の治療が全身の炎症負荷を減らし、糖尿病による合併症(腎臓病)の悪化を防いだ可能性を示唆しています。
以上のように、糖尿病と歯周病は互いに原因にも結果にもなり得る密接な関係であり、まさに双方向にリスクを高め合う間柄なのです。
最新研究が示す双方向リスクの改善効果
こうした糖尿病と歯周病の双方向関係については、近年の研究によってますます裏付けが強まっています。以前から、糖尿病のある人が歯周病を治療すると血糖値が改善する傾向があることが指摘されてきました。例えば歯周病の治療後にHbA1cが改善したり、インスリンの必要量が減ったりするケースが報告されています。これは歯ぐきの慢性炎症を取り除くことで全身の炎症反応が和らぎ、インスリン抵抗性が改善するためと考えられます。逆に最近の画期的な研究では、糖尿病治療を強化して血糖コントロールが良くなると歯周病の状態も改善することが初めて明確に示されました。東京医科歯科大学などのグループが行ったこの研究では、血糖管理が難しかった2型糖尿病患者さんを対象に集中的な治療と生活習慣改善を行ったところ、平均HbA1cが約9.6%から7.4%へと大幅に低下し、それに伴って歯周ポケットの深さや出血の指標など歯周病の諸症状も有意に改善したのです。この結果は、高血糖が誘発していた歯周組織の炎症が、糖尿病治療によって抑えられたことを意味します。つまり**「血糖値を改善すれば歯周病が良くなり、歯周病を治療すれば血糖値が良くなる」**という双方向の改善効果が科学的に証明されつつあるのです。
最新の知見はこれだけではありません。冒頭で触れたように、糖尿病と歯周病の両方を抱える人では心血管疾患や死亡のリスクが高まることが報告されています。裏を返せば、歯周病のケアは糖尿病患者さんの命と生活の質を守るうえでも重要といえるでしょう。さらに世界的な動きとして、歯科と内科の連携による包括的なケアの必要性が提唱されています。例えば欧州歯周病学連盟(EFP)は「歯科医療者は糖尿病患者のケアチームの一員」であるべきだと強調しており、歯科の場で糖尿病スクリーニングを行う試みや、内科医と歯科医が情報共有して患者を診る体制づくりが進められています。日本でも、歯科医院で血糖測定をして糖尿病の疑いがある患者を早期に内科紹介するといった取り組みが研究されています。このように医学界全体で、糖尿病と歯周病を一体のものとしてとらえケアしていこうという流れが加速しているのです。

糖尿病と歯周病から身を守る実践アドバイス
それでは、糖尿病をお持ちの皆さんが日常生活で歯周病を予防し、あるいは歯周病の悪化を防ぐためには具体的に何ができるでしょうか。ここからは実践的なアドバイスをいくつかご紹介します。ポイントは、血糖管理と口腔ケアの両面からアプローチすることです。
まず第一に、血糖コントロールを良好に保つことが基本です。高血糖状態をできるだけ避けることで、歯ぐきの免疫低下や炎症の悪循環を防ぎます。主治医の指示に従った食事療法・運動療法・薬物療法で適切な血糖管理を続けましょう。最近の研究結果が示すように、血糖値が改善すれば歯周病も良い方向に向かう可能性があります。特にHbA1cの高い方や糖尿病予備軍と言われた方は、放置せず積極的に改善に取り組むことで将来の歯周病リスクも下げられるかもしれません。
次に、歯周病そのものの予防・治療にも力を入れましょう。具体的には毎日の丁寧な歯みがきとフロス(糸ようじ)などでプラークをしっかり除去し、歯ぐきを清潔に保つことが大切です。歯周病は初期には自覚症状が乏しいため、定期的に歯科健診を受けて早期発見・早期治療することも欠かせません。糖尿病のある人は特にかかりつけの歯科医を持ち、少なくとも年に1~2回は歯周病のチェックとクリーニングを受けることが両方の病気管理に有効だとされています。歯ぐきから出血する、腫れている、歯がグラつく、といった症状がある場合は我慢せず早めに歯科を受診しましょう。専門的な歯周病治療(スケーリングやルートプレーニングなど歯石除去・清掃の処置)を受けることで、炎症を抑えて歯周病の進行を止めることができます。その結果、歯周病の改善だけでなく血糖値の安定化にも良い影響が期待できます。
また、医科と歯科の連携も忘れてはなりません。糖尿病の主治医と歯科医にそれぞれ自分のもう一方の病状を共有し、必要に応じて情報交換してもらうようにしましょう。歯科医には糖尿病であることを必ず伝え、治療方針の参考にしてもらいます。内科医には歯周病の治療状況や口腔内の状態を報告し、場合によっては歯科から所見を書いてもらっても良いでしょう。お互いの専門家が連携することで、あなた自身の体全体をトータルにケアする体制が整います。幸い近年は「チーム医療」の重要性が認識され、糖尿病と歯周病に対する協力体制が広まりつつあります。遠慮せず医師・歯科医に相談し、自分自身がチームの一員になったつもりで積極的にケアに参加しましょう。
最後に、生活習慣の見直しも重要です。糖尿病と歯周病に共通する危険因子として、喫煙やストレス、睡眠不足、偏った食事などが挙げられます。喫煙は歯ぐきの血行を悪くし歯周病を進行させるだけでなく、インスリン抵抗性も高めて糖尿病を悪化させます。できる限り禁煙に努めましょう。栄養バランスの良い食事や十分な睡眠も、体の免疫力維持と血糖安定のために大切です。ビタミンやミネラルを豊富に含む食品を摂り、口腔内の粘膜や免疫を健康に保つことも心がけてください。
まとめ
糖尿病と歯周病の関係は、かつては見過ごされがちでしたが、現在では互いに深く影響し合う双方向関係であることが明らかになっています。糖尿病があると歯周病が悪化しやすく、逆に歯周病があると糖尿病の管理が難しくなる――まさに悪循環を起こし得る組み合わせです。しかし裏を返せば、歯周病をきちんと治療すれば糖尿病が改善し、糖尿病を適切に治療すれば歯周病も良い方向に向かう可能性があります。この双方向リスクを理解し、日頃から血糖コントロールと口腔ケアの両面に取り組むことが、健康寿命を延ばす秘訣です。
糖尿病をお持ちの方はぜひ今日から、歯と歯ぐきにもこれまで以上に目を向けてみてください。定期的な歯科受診と毎日のケアで歯周病を防ぎ、同時に糖尿病の合併症リスクを減らしましょう。幸い医学は日々進歩し、糖尿病と歯周病のケア方法も充実してきています。適切な治療とセルフケアを続ければ、両方の病気に負けない明るい未来がきっと拓けるはずです。あなたの笑顔と健康を守るために、今日からできる一歩を踏み出してみませんか。専門家のサポートを受けつつ、自分自身の歯と体を大切にしていきましょう。糖尿病と歯周病という二つの課題に立ち向かう皆さんを、私たちも全力で応援しています。